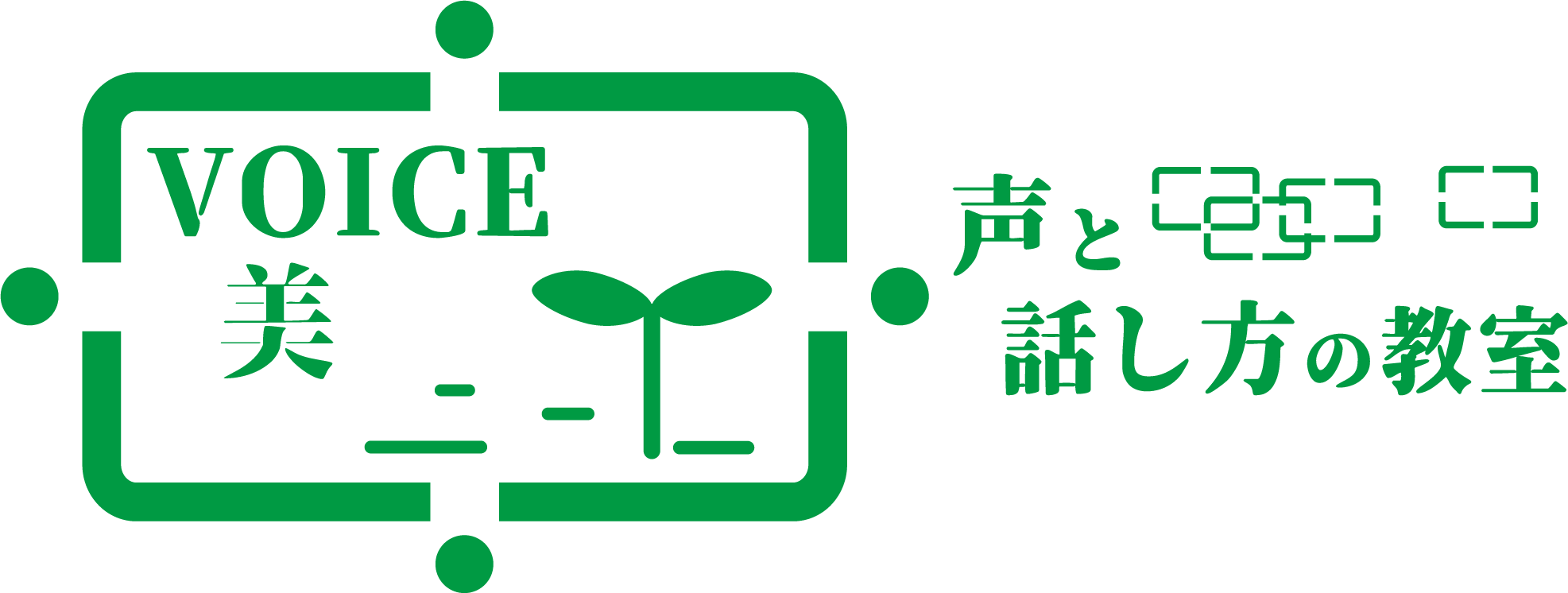プレゼンやスピーチで、大事なポイントが伝わらない原因はリズムにあった!?【大阪/マンツーマン/ボイトレ・話し方教室】
ご覧いただきまして、ありがとうございます。
ビジネスパーソンのための「声と話し方の教室」講師の砂川顕子です。
ビジネス向けボイストレーニング・話し方教室。
プレゼンテーション、スピーチ、発表、セミナー、司会、ファシリテーション、商品説明、動画撮影、会議での発言等のスキル向上!
発声、滑舌、抑揚、話の組み立て、言いまわし表現等、ビジネスで必須の”話すスキル”をつけて伝えたいメッセージを自信を持って表現しましょう!
皆さんは、話をする時の”リズム”って
意識されたことがあるでしょうか。
音楽だけじゃなく、話にも”リズム”があるんです。
そして、聞いている側は、
変化のない一定のリズムの話を聞き続けていると
まるでBGMのように
頭の上の方で流れている”音”になってしまう可能性が高いんですね。
飽きちゃう、眠くなっちゃう話というのは、
そういう要素も大きいです。
同じリズムの話を、ずーっと聞き続けて、内容を把握することは、
聞き手にとっては集中力が必要なんです。

対して、話のリズムに適切な変化がついていると、
聞き手は飽きなくなります。
そこまで頑張って集中していたわけじゃないけど
最後まで面白く話を聞いていた、よく理解できた、という場合には、
聞き手の心をつかむリズムの変化がついているものです。
さて、ここで言う”話のリズム”とは、
抑揚などの表現でもつけることができますが、
一番簡単で、大きく変化をつけられるのが
一文(句点「。」がついて話し終わるまで)の長さを変えることです。
そして、一文の長さを変えようとすると
必然的に、語尾などの言いまわしも変えることになり、
より表現に変化がつくのです。
それでは、例として、まず
“リズムが一定”の話を挙げてみようと思います。
できれば、声に出して言ってみてください。
話すリズムが一定の例

『河や海の汚染の原因第1位は、生活排水で、その中でも、台所排水が、一番家庭から多く出る汚水ですから、下水処理は普及していますが、各家庭で汚れた水を流さないようにしましょう。
特に、台所から出る食べ物の残りや、食用油の残りなどを含んだ排水は、水質汚濁の大きな原因になっていますので、食べ物を作りすぎない、残さない習慣や、油は固めて捨てるなど、一人ひとりの取り組みが必要です。』
いかがでしょうか?
2つの文(「。」までを一文として)がありますが、
どちらも同じような長さで
文の表現も似ていて
ダラダラと話している印象を受けませんか?
これでは、話を理解するために、
聞き手のほうが頑張って頭を働かせ、集中しなければなりません。
続いて、同じ話で、
一文の長さを変えて、リズムに変化をつけてみます。
これも、できれば声に出して言ってみてください。
話すリズムに変化をつけた例

『河や海の汚染の原因第1位は、なんだと思われますか?
第一位は、生活排水です。
その中でも、台所排水が、一番家庭から多く出る汚水です。
下水処理が普及しているとはいうものの、やはり各家庭で汚れた水を流さないようにしましょう。
特に、台所から出る食べ物の残りや、食用油の残りなどを含んだ排水は、水質汚濁の大きな原因になっていますので、食べ物を作りすぎない、残さない習慣や、油は固めて捨てるなど、一人ひとりの取り組みが必要です。』
最初の内容(一文)を4つの文に分けたことで、
それぞれが短くなりました。
特に、『〇〇です』と短く言い切っているところは
メリハリがついて、大事なポイントとして際立つので、
聞き手に伝わりやすくなります。
このように、大事なところや、注目してほしいところは
あえて一文を短くするなど、リズムを変えることで、
聞き手にすんなりと言いたいことが伝わるようになるのです。
まとめ
話す側としては、
自分の中に染みついている一定の表現やリズムで、ずっと話している方が
ラクなのかもしれません。
ですから、話のリズムを変えるというのは
意識しなければできないことです。
まずは、
「大事なところ、注目してほしいところは、一文を短く、言い切る」
をやってみましょう。
一文の長さに変化をつけようとすることで、
言いまわしの表現も身につくようになりますよ。