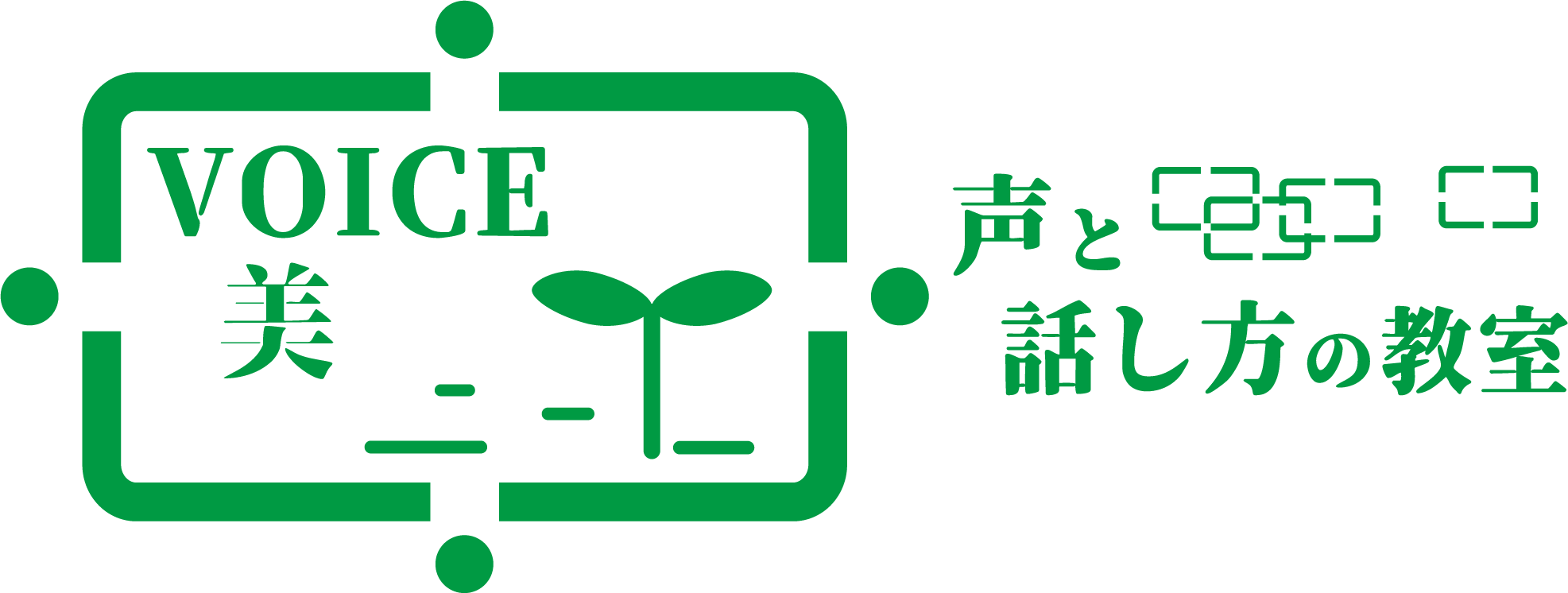話がぼんやりして説得力がない原因とは?【大阪/マンツーマン話し方教室】
ご覧いただきまして、ありがとうございます。
ビジネスパーソンのための「声と話し方の教室™」講師の砂川顕子です。
きちんと話をされているのに、
聞いていてなんだか説得力に欠ける人がいらっしゃるんです。
話している内容は理解できるけれど、
聞いていて”納得感”がない状態ですね。

その原因の一つとして、
“話のつながり”が関係していると思い当たりました。
細かい部分で
話がつながっているようで、つながっていないんですね。
そのため
聞き手がすんなり納得したり
腑に落ちたりするための”話の道筋”が、
太く明確になっていないんです。
(ロジックが甘いとでも言いましょうか・・)
では、例題をあげてみたいと思います。
微妙につながっていない”話”
まずは、
つながっているようで、微妙につながっていない”話”
の例をあげてみます。
オフィスにおいても、「CO2排出量の削減」を目標にすることになりました。
そこで、皆さんには、クールビズ・ウォームビズの活用と、
昼休みや残業時間帯の不要照明の消灯にご協力をお願いします。
上記の”話”の例では、必要最低限のことは言っていますね。
でも、
話がつながっているようで、つながっていないのが
お分かりいただけますか?

ここでは、まず、オフィスでの目標として
①「CO2排出量の削減」を挙げています。
そのうえで、皆さんにやってほしいことを2つ言っています。
②「クールビズ・ウォームビズの活用」と「不要照明の消灯」です。
①CO2排出量の削減 ⇒ ②クールビズ・ウォームビズと、不要照明の消灯
という話の流れは、内容としては、齟齬はありません。
話を聞いている方としても、おかしいとは思いません。
ですが、
①⇒②をつなぐ”情報”が抜け落ちていて、
聞き手の知識と推察に頼った内容になっているのです。
聞き手が、じっくりと内容を吟味できる時間があるならいいのですが、
“話”という、短い情報がすぐに流れていく場面では
聞き手の頭が追い付かず、
「なんとなくは分かるけれど、ぼんやりとした納得感のない話」
になりかねません。

情報と情報に、はっきりと”つながり”を持たせる
先に挙げた例では、
本来なら、下記のようにAとBの情報を挟むことで、
やっと①と②がつながります。
①CO2排出量の削減 ⇒
⇒ A)火力発電所から出るCO2を減らすための節電 ⇒
⇒ B)オフィスでエアコンや照明の使用を減らす ⇒
⇒ ②クールビズ・ウォームビズと不要照明の消灯
そこで、”話”の中にも、
上記A・Bの情報を適切に盛り込んでみます。
オフィスにおいても、「CO2排出量の削減」を目標にすることになりました。
CO2を削減するために、オフィス内で取り組めることといえば、節電です。
そこで皆さんには、エアコンの温度設定を抑えるために、クールビズ・ウォームビズを活用していただきたいと思っています。
また、昼休みや残業時間には、いらない電気は消していただくように、ご協力をお願いします。
上記の”話”では、青字部分を内容として付け足しました。
情報を少し付け足したことで、
「CO2の削減」という目標に対しての行動である
「クールビズ・ウォームビズ」「不要照明の消灯」が
すんなりとつながりました。
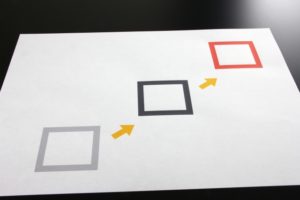
このように
情報と情報との間に、はっきりとしたつながりを持たせるように話すことで、
聞き手は難なく納得できたり
説得力のある話になったりするのです。
まとめ
話をする時に
「情報と情報とをつなげるための言葉」がないせいで
「なんとなくは内容は分かるけれど、納得感に欠ける話」
になっていないか、気を付けてみましょう。
これは、長々と話を付け足す必要は全くなくて、
ちょっとした一言、ちょっとした情報を盛り込むだけで
格段に分かりやすくなったり、説得力が出たりするものです。
情報の”つながり”をあいまいにして
聞き手の知見や想像に頼ったりせず、
一本筋の通った話をしたいものです。