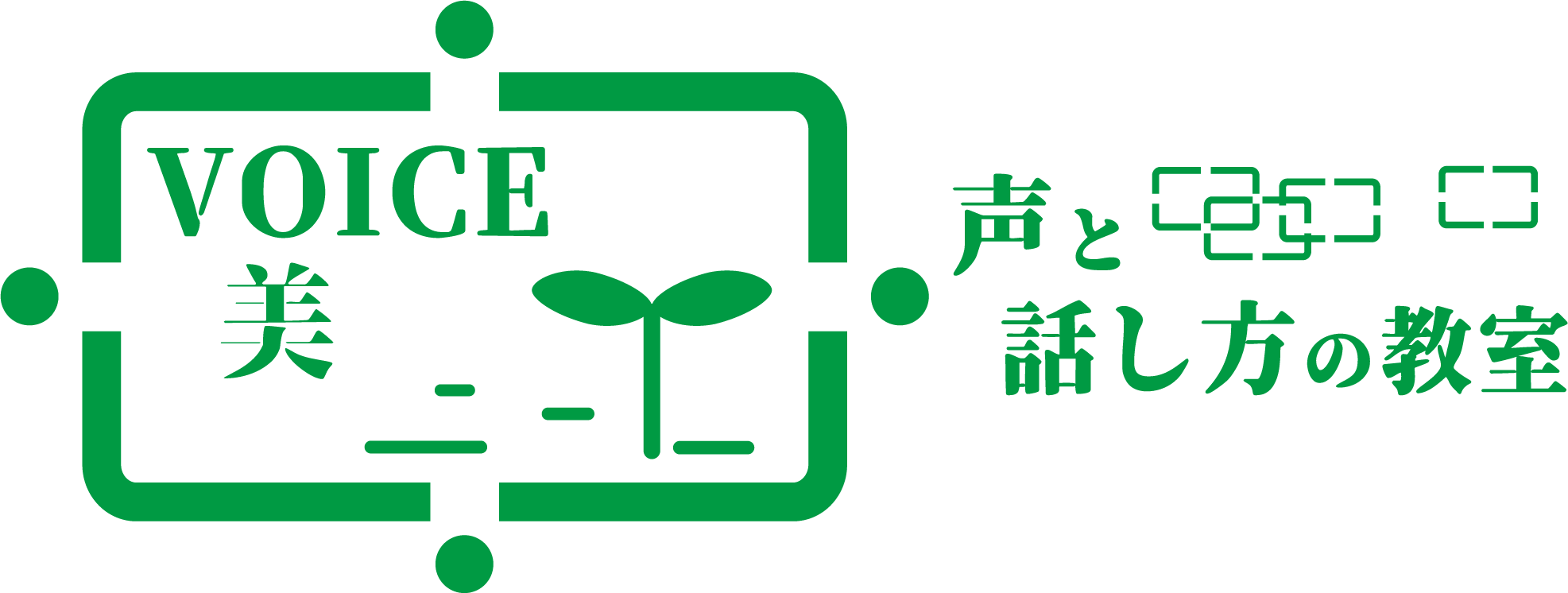「良い声」で話すだけでは、聞き手の心はつかめない【大阪/マンツーマン話し方教室】
ご覧いただきまして、ありがとうございます。
ビジネスパーソンのための「声と話し方の教室™」講師の砂川顕子です。
「良い声」で話す人の話は、
聞いていて心地いいですよね。
聞きやすい声だと
自然と話に耳を傾けてしまうものですから、
良い声の人をうらやましく思うこともあるのではないでしょうか。
でも、プレゼンやセミナーなど、長く話す場面になると、
「良い声」だけでは
聞き手の心をつかむことができないんです。
なぜなら、
「良い声」で
同じトーンで
同じリズムで
話し続けられると、
聞き手は心地よすぎて睡魔が襲ってきたり
頭がぼーっとしてきたりするからです。
つまり、聞き手のリラックス神経を刺激してしまうんですね。
せっかく声を磨いて、一生懸命喋っても、
眠りを誘うBGMになってしまうのはいただけませんよね。
長く話していても、聞き手の心をつかみ続けるには、
「声の表現」ができるようになる必要があるのです。
「声の表現」とは
声の表現とは、まず簡単に言うと「話の抑揚」です。
話をしながら
声の高さや、強弱、声色、スピードなどに変化をつけて
自分の言いたいことが一層伝わるように工夫するのです。
声の表現をしていない人は、
どれだけ「良い声」で、良い事・大事な事を言おうが
どれも同じに聞こえてしまって、
言いたいことが伝わらなくなります。
特に、一人で長く話す時には、
退屈をされたり、聞き流されたりしかねません。
また、よく勘違いされることですが、
「抑揚がない=棒読み」とも限らないのです。
棒読みには聞こえなくても
抑揚がない話し方の人はたくさんいますし、
抑揚がついていたとしても
「話し癖」のような不適切な抑揚は、伝わる弊害になります。
同じような抑揚が繰り返される話し方は
抑揚がない話し方と同じで、
どんなに「良い声」でも飽きられるのです。
また、抑揚だけにとどまらず、
話す時のリズムも大切です。
毎回同じタイミングで
同じ長さの間(ま)を取る話し方は、
リズムが一定に感じられてしまいます。
また、話すスピードがずっと一定なのもそうですね。
話す内容に合わせて、話す時のリズムに変化をつけることも、
聞き手の心をつかむための要素のひとつです。
このように、「良い声」で話したなら
瞬間的には聞き手の心をつかめるかもしれませんが、
長く話すとなると、声そのものの魅力だけでは不十分なんですね。
「良い声」だけで終わらない・退屈されないコツ
せっかくお持ちの良い声や
磨いて手に入れた良い声を生かすために、
声を使って表現できるようになりましょう。
特に、ビジネスの場面での表現は、
「感情表現」よりも「主旨表現」が多くなります。
すなわち、
話の中の大事なポイントや、伝えるべきことが
伝えたいニュアンスで正確に伝わるための表現です。
もちろん「言葉選び」も大切ですが、
その言葉を、どう声で表現して紡いでいくかによって
伝わり方が変わってくるのですね。
声の表現として、まずは簡単なところから、
- 時には短く言い切る
- 話の変わり目では長めに間(ま)をとる
- 難しい説明はペースを落とす、余談はテンポよく
- 数値データや固有名詞など大事な語句は、少し高めの声でゆっくりはっきり発音
を心がけてみましょう。
また、話しながら
どこで無意識に間(ま)をとっているのか
自分の癖に気付けるようになりましょう。
聞き手の心をつかむ伝わる話をするためには、
「聞き手まで届く良い声」と「声の表現」
いずれもが欠かせない要素です。
聞き手まで届く声というのは、
一般的な「良い声(エエ声)」である必要はありません。
高い声・低い声など元々お持ちの声がどんな声であろうが、
ハリのある、聞き手の耳にすんなり入っていくような良い響きの声であることが大切です。
「エエ声」を目指すのではなく、
聞き手の心をつかむ声で表現することを
目指していただきたいと思います。