分かりやすく話すために、間(ま)の長さと、その効果を理解しよう【大阪/マンツーマン/ボイトレ・話し方教室】
ご覧いただきまして、ありがとうございます。
ビジネスパーソンのための「声と話し方の教室」講師の砂川顕子です。
ビジネス向けボイストレーニング・話し方教室。
プレゼンテーション、スピーチ、発表、セミナー、司会、ファシリテーション、商品説明、動画撮影、会議での発言等のスキル向上!
発声、滑舌、抑揚、話の組み立て、言いまわし表現等、ビジネスで必須の”話すスキル”をつけて伝えたいメッセージを自信を持って表現しましょう!
今回は、
話の間(ま)は
使いどころと長さによって、効果が違ってくる
という内容で書こうと思います。
(最後に、音声サンプルもあります)
ただ単に「話の間(ま)を取る」といっても、
的外れなタイミングで
常に同じような長さの間(ま)を取っていては、
伝わる話になりえません。
「ここで取る話の間(ま)は
どういう効果を持たせるためなのか」
を話す側が理解したうえで
話の内容によって
適切なタイミングで、適切な長さで取る必要があるのです。

では、間(ま)が”話”に与える効果として
代表的なものを3つ挙げましょう。
- 話の構成を示して、聞き手の頭を整理する
- 聞き手が理解する時間を作る
- キーワードを強調する
それでは、まず例題を提示します。
<1>『新製品の特徴は、2つあります。』
<2>『1つめの特徴は、耐水性の強化、つまり、より水に強くなったことです。』
<3>『水中に24時間沈めておく、耐水テストもクリアしております。』
<4>『2つめの特徴は、顔認証がより高性能になったことです。』
<5>『めがねや帽子を着用していても、正しく本人だと認識できております。』
上記の<1>~<5>の流れの”話”において、
皆さんは、どこで間(ま)を取られるでしょうか?
どこで間(ま)をとるのが効果的か
話の間(ま)の効果別にみていきたいと思います。
1.話の構成を示して、聞き手の頭を整理する
まずは、話の構成をはっきりとさせるためにとる間(ま)です。
話の構成が明確になると
聞き手は、頭を整理しやすくなり
一つ一つ順番に理解しながら聞いていくことができます。

上記に提示した“話”の内容から、構成をアウトラインで示すと、
<1>序章
<2>第一章
<3>第一項
<4>第二章
<5>第一項
このような形になるでしょうか。
ですから、章(同じ内容のまとまり)が分かりやすくなるように、
- <1>の後
- <3>の後
には、長めの間(ま)を入れる必要があります。
2.聞き手が理解する時間を作る
聞き手は、話を“音”で聞いた後、
それを脳で“意味づけ”することで内容を理解していきます。
この「音→意味づけ→理解」の過程は
簡単な内容であれば一瞬で行われますが、
複雑な内容であったり
たくさんの情報(”音”)が一気に入ってきたりすると、
少し時間がかかることもあります。

そこで、話す側が間(ま)をとって
聞き手が理解するまでの時間を作る必要があるのです。
これは簡単には
文章でいう読点「、」や句点「。」のところで間をとればよいです。
簡単そうですが、
意識していないと、意外とできていないことも多いです。
特に、読点「、」では間(ま)をとっているけれど、
句点「。」で充分に間(ま)をとれていない人が多くいらっしゃる印象です。
話が「。」で終わった後、すぐに次の話に入ってしまうと、
聞き手も焦ってしまいます。
句点「。」箇所では、聞き手のほうを見て
「理解できたかな?」
と一瞬確認する程度の間(ま)とるイメージで話してみましょう。
3.キーワードを強調する
最後は、キーワードを強調するための間(ま)です。
強調するための間(ま)は、
息継ぎもできないくらいごく短い間(ま)にしなければなりません。
長めの間(ま)をとってしまうと
話の流れが途切れてしまうからです。

では、もう一度、同じ例題を表示しましょう。
<1>『新製品の特徴は、2つあります。』
<2>『1つめの特徴は、耐水性の強化、つまり、より水に強くなったことです。』
<3>『水中に24時間沈めておく、耐水テストもクリアしております。』
<4>『2つめの特徴は、顔認証がより高性能になったことです。』
<5>『めがねや帽子を着用していても、正しく本人だと認識できております。』
上記の”話”の場合、
内容の要として言いたいのは、
2つの特徴である
『耐水性の強化』
『顔認証がより高性能』
ですよね。
そこで、この2つのキーワードを話の中で際立たせるために
ごく短い間(ま)を活用します。
<2>『1つめの特徴は、()耐水性の強化()、つまり、より水に強くなったことです。』
<4>『2つめの特徴は、()顔認証がより高性能に()なったことです。』
上記の()のところで、ごく短く間(ま)をとることで、
間(ま)に挟まれたワードを話の中で際立たせる効果があります。
音声サンプル
では、まず間(ま)がとれていない音声をお聞きください。
※音量をミュートにしていますので、小さめの音量から出してください。
続いて、上記に挙げた3つの効果を元に
間(ま)を適切にとった音声をお聞きください。
※音量をミュートにしていますので、小さめの音量から出してください。
話の間(ま)だけの効果を感じていただくため
どちらも、あえてちょっと単調に話してみました。
間(ま)をとっていないと
話の構成が分かりづらく、話が次々と展開されて
理解するのに集中力が必要なのがお分かりいただけるでしょうか。
また、間(ま)がないと、
大事なキーワードが、単調な話の中に埋もれてしまうのも
気づいていただけたら幸いです。
まとめ
話の間(ま)は、
聞き手に与える効果を考えながら、とる長さを調整していくことで
分かりやすく、伝わりやすい話になります。
- 話の構成を示して、聞き手の頭を整理する
- 聞き手が理解する時間を作る
- キーワードを強調する
という、3つの効果をしっかりと活用できるように、
“聞き手のために”間(ま)をとれるようになりましょう。
自分はしっかりと間(ま)をとったつもりでも、
聞き手からしたら、大してとれていない場合もありますから、
録音して聞いてみるのもおすすめします。
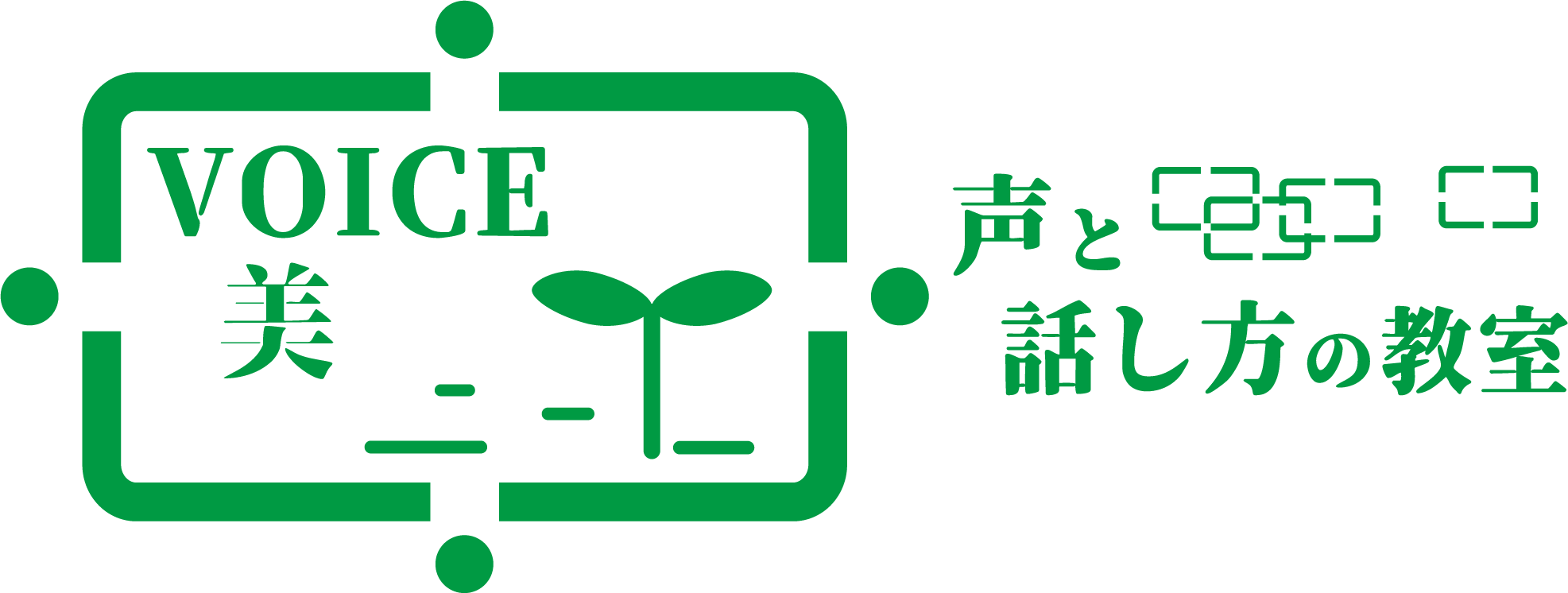


“分かりやすく話すために、間(ま)の長さと、その効果を理解しよう【大阪/マンツーマン/ボイトレ・話し方教室】” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。