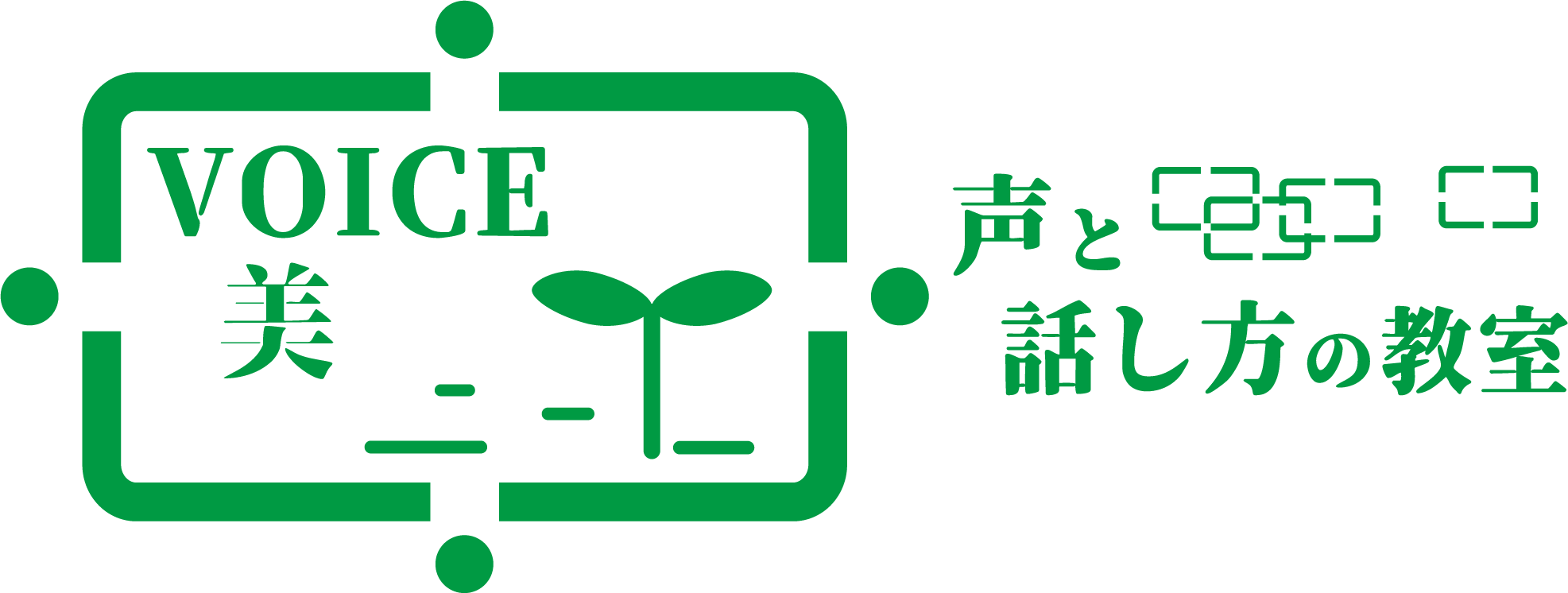説得力のある話にするために、話の”筋とつながり”を考えましょう【大阪/マンツーマン/ボイトレ・話し方教室】
ご覧いただきまして、ありがとうございます。
ビジネスパーソンのための「声と話し方の教室」講師の砂川顕子です。
ビジネス向けボイストレーニング・話し方教室。
プレゼンテーション、スピーチ、発表、セミナー、司会、ファシリテーション、商品説明、動画撮影、会議での発言等のスキル向上!
発声、滑舌、抑揚、話の組み立て、言いまわし表現等、ビジネスで必須の”話すスキル”をつけて伝えたいメッセージを自信を持って表現しましょう!
今回のテーマである「話の筋とつながり」は、
プレゼンテーション・スピーチ・セミナー講師・会議での発言などなど
様々な”話”において、大切なことです。
“筋とつながり”が明確でない話は、
論点がぼやけてしまうため
聞き手の納得感を引き出すことができず、
心に届かなくなってしまいます。
話し始めて、色々と喋っているうちに
どんどん論点がずれていってしまう・・・
という経験は、
カンの良い人なら思い当たることがあるのではないでしょうか。

また、自分では気づかず
無意識に筋の通らない話をしてしまっていることも
あるのではないかと思います。
では、筋の通った説得力のある話をするには
どうすればよいのか?
例題を挙げて説明していきますね。
まずは、良くない例です。
例1:話の”筋とつながり”が明確でない
『熱中症の予防には、なんといってもこまめな水分補給が大切です。
また、汗をかいた時には、ミネラル豊富な麦茶もおすすめですよ。
もし、熱中症の症状が出てしまったら、経口補水液を飲みましょう。
熱中症にならないために、しっかりと対策をとってください。』
音声で”話”としてお聞きください。
※音声をミュートにしていますので、小さめの音量から再生してください。
上記の例1では、熱中症の話をしていて
一文ずつの意味も分かります。
一見(一聞?)特に分かりづらくはない話に聞こえるでしょう。
ですが、一つ一つの情報がバラバラに与えられているため、
聞き手は、その場で「ふーん」と聞き流してしまう可能性が高いです。

そして、初めに「熱中症の予防」の話かと思いきや、
途中で「熱中症の症状が出てしまったら」という
熱中症になった時の対処の話をしています。
最後は「熱中症にならないために」でまとめているので、
結局、熱中症予防の話なのか、
熱中症になった時の対処法の話なのか、
筋が一本通っていません。
文字に起こすとよく分かることでも、
話していると、このように論点が微妙にずれてしまうことは
容易に起こり得るのです。
聞き手からしても、
「熱中症」の情報には変わりないので、特に違和感なく聞くものの、
納得感や説得力が感じられないまま、聞き流して終わり
という状態になりがちです。
これを、説得力のある話にするには、
もっと“論点・観点を絞る”ことが大切です。
では、次の例では、“熱中症予防”に論点を絞ったうえで、
さらに一つ一つの話に”つながり”を持たせてみます。
例2:話の“筋とつながり”のある例
『熱中症の予防には、なんといってもこまめな水分補給が大切です。
また、汗をかいた時には、水分だけでなく、塩分やミネラルが必要ですから、ミネラル豊富な麦茶がおすすめです。
今話題の経口補水液は、熱中症の症状が出た時に飲むもので、予防としては向いていません。
正しい情報をもとに、熱中症にならないための対策をしっかりととってください。』
音声で”話”としてお聞きください。
※音声をミュートにしていますので、小さめの音量から再生してください。
上記の例2では、初めに水分補給の話をしていますから、
2段落目では、『水分だけでなく』麦茶がよい、
というように、直前の話と“つながり”を持たせています。
また、2段落目で、
『ミネラル豊富』という語句が唐突に出てこないようにしました。
『汗をかいた時』と『ミネラル豊富な麦茶』という2つの情報がたやすくつながるよう、
『塩分やミネラルが必要』という補足を入れています。
さらに、経口補水液の話は、
『予防としては』向いていない、という風に
“熱中症予防”の観点から述べています。
そして、熱中症の予防として、良いもの・向かないものを述べことから、
これを受けて最後に『正しい情報を元に』対策をとるよう、
言って、これまで述べたことをまとめています。
こうして、話の論点を絞って、
一つ一つの話がつながるように述べていくことで、
聞き手にとって納得感のある話になります。

まとめ
説得力のある話をするためには、
- 話の論点・観点を絞ること
- 一つ一つの話がつながるように話すこと
- 唐突に出てくる単語がないように補足すること
を心がけてみてください。
『ふ~ん』で終わっていた話を、
もっと関心をもって聞いてもらえるように工夫しましょう。