話が伝わらない最大の原因とは?【大阪/マンツーマン話し方教室】
ご覧いただきまして、ありがとうございます。
ビジネスパーソンのための「声と話し方の教室™」講師の砂川顕子です。
職業柄、たくさんの人の話し方を分析する機会が多いのですが、
“話が伝わらない”原因は
人それぞれに様々な要素がミックスされているものです。
様々な要素というのは、例えば、
- 声が届かない
- 滑舌がはっきりしない
- 抑揚が適切につかない
- 言葉数が多い or 足りない
- 話す順番が適切でない
- 言葉や表現の選択が適切でない
- 話すペースが速い or 一定
などなど。
細かく言えば、このほかにもあるのですが、
これだけを見ると、
「伝わる話し方」をするのって
難しいと感じられるかもしれません。

でも、これらを包括した
話が伝わらない”最大”の原因があるのです。
それは、
「話す人が、言葉に意味づけをしていないこと」です。
言葉に意味づけをしていないとは?
このブログでも何度か触れていることですが、
口から発する言葉って、単なる”音”です。
例えば、
『この商品は、アレルギーを発症する原材料を使用していません』
と言う時・・
話す側が
- 原稿や資料の文字を読み上げているだけ
- 次に言うことを考えながら言葉を発する
ような状況であれば、
「ただの”音”を口から発しているだけ」に近くなります。
『このしょーひんはあれるぎーをはっしょーする・・・』
という”音”ですね。

その”音”を聞いて、
聞き手が自分の中で
“音” → ”意味のある言葉”
へと変換して理解してくれたり、
逆にその気がなかったら
単なる”音”として聞き流したりするのですね。
『使用していま・・』
と文末が聞き取りづらかったとしても、
聞き手は、話の流れから、
きっと『使用していません』と言ったのだろう
と推測して理解することもよくあります。
“音”に対する意味付けを、聞き手にゆだねている時点では、
当然、聞き手は、自分が聞きたい情報しか受け取らないし、
自分なりに解釈して終わるでしょう。
つまり、
話す側の「伝えたいこと」「伝えなければならないこと」は伝わらないので、
誤解が生じたり
後から「言った・言わない」の論争になったり
しかねないのですね。

言葉に意味づけをするには、言葉に焦点を当てる
話す側が
言葉に”意味づけ”をして、口から発することで、
聞き手には
“音”ではなく、”意味”として届きます。
先ほどと同様に、
『この商品は、アレルギーを発症する原材料を使用していません』
と言う時を例に挙げましょう。
『この商品』
と口にする時には
どの商品なのかがはっきりと分かるように、
手差しをするなり、直前の話とつながるように表現するなりして
自分と聞き手とで、理解を共有できるようにする。
また、聞き手の方を見て
理解を共有できているか確認する
という気持ちが必要です。
さらに、
『アレルギーを発症する原材料』
と口にする時には、
実際に、アレルギーのことや
アレルギーを発症する原材料を頭にイメージすると同時に、
聞き手の反応を見て、
「アレルギーを発症する原材料の具体例」を言った方がいいのか
言わなくても理解できるか
などを確認します。
『使用していません』
と口にする時には、
最後の『いません』という否定形を
一番言いたいこととして届けるように言います。

このように、
「日本語を発音しさえすれば、理解してもらえるだろう」
ではなく、
「言葉に、自ら意味づけをして発することで
やっと日本語の”意味ある言葉”として受け取ってもらえる」
という認識に変えることができれば、
話がもっと伝わるようになるのです。
「心を込めて話す」とよく言いますが、
これは「大げさに演技するように話す」ということではなくて
「一つひとつの言葉や表現に、自らの中で焦点を当てて
意味づけをしてから発する」ということです。
「言葉の意味」も、「言いたいこと」も、
話す側がその”意味”に焦点を当てないまま
なんとなく口にしても、伝わるわけがないのですね。
まとめ
こうして、一つ一つの話を
自ら意味づけをして口から発するように心がけることで、
自然と、聞き手まで届く声になったり
滑舌がはっきりしたり
抑揚がついたりもするのです。
また、併せて、
話しながら聞き手の反応を確認できるようになると、
・分かりやすい話の順序
・言葉の選択
・話すペース
なども
聞き手に合わせて適切に変えられるようになっていきます。
話す時に、単なる”音”を聞き手に届けていないか?
ご自身のお話を振り返ってみてくださいね。
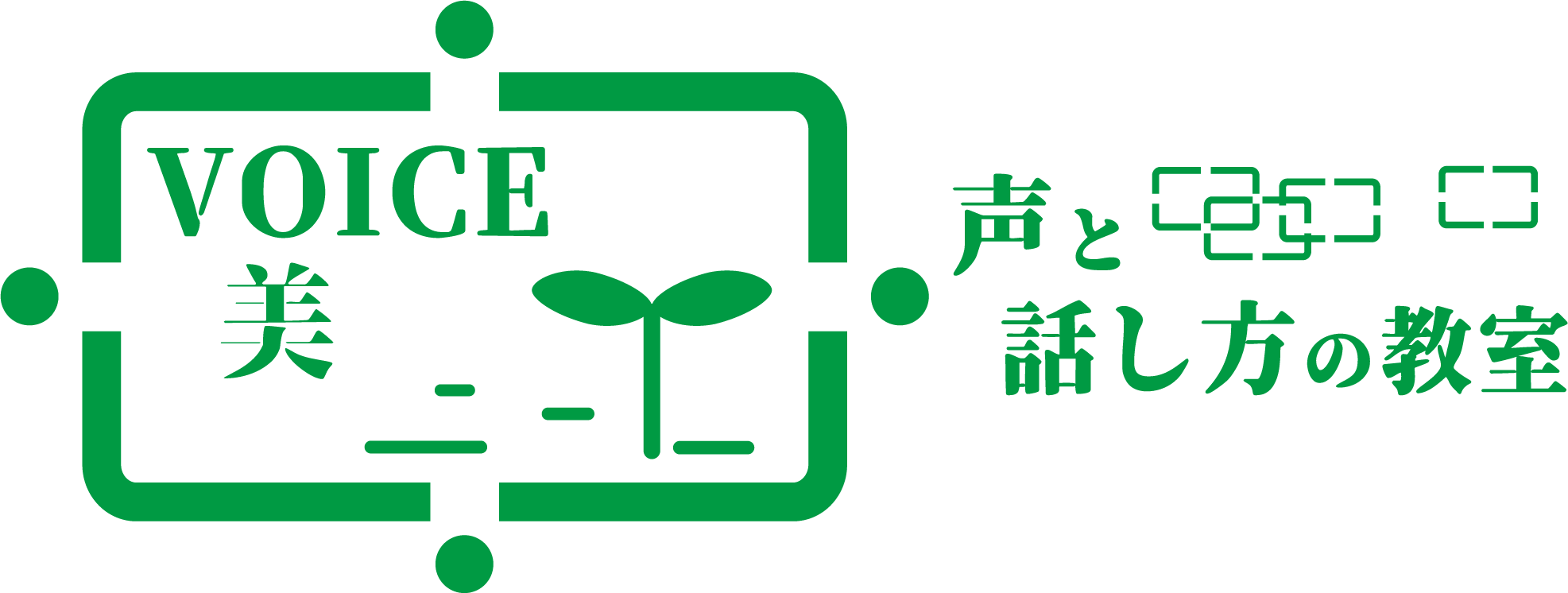

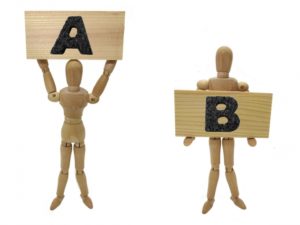
“話が伝わらない最大の原因とは?【大阪/マンツーマン話し方教室】” に対して1件のコメントがあります。
コメントは受け付けていません。